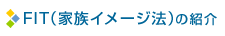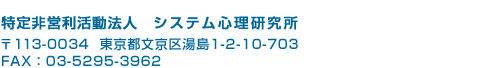直線的認識論から円環的認識論へ
システム心理学は,文字どうりの“フロンティア”である.しかし,その成立には,<臨床の知>の発想の先駆けとも言える,新しい認識論,つまり“円環的認識論”の登場が深く関わっていた。1950年代に,統合失調症の家族研究を推進したベイトソン(G.Bateson、1979)は,前述した中村の主張と同様の指摘を行い,その発想の根拠を円環的認識論(circular epistemology)と呼び始めた.彼は,二元論や還元主義的思考を一まとめにして,直線的認識論と称して批判し,それを超克する思考法として円環的認識論を位置づけた.その主張によれば,記述しようとする現象の部分や小片を取り出して,ある部分が他を統制する,あるいは,ある特定の部分が他の現象を引き起こす“原因”になるなどと結論づけることは,直線的認識論に縛られたものにすぎない.そのような認識論的態度や傾向は,一見,科学的ないし論理的に見えているが,実は自然なひとまとまりの“生態系”を切り刻むことにしかならず,科学研究者としてはむしろ,避けるべきだと言うのである(亀口、1997).
この主張をシステム臨床心理学(システム心理学のなかでも臨床的課題を主に追求する領域)で扱う事象に当てはめると,次のようになる.たとえば不登校を例に取ると,直線的認識論では,不登校という“結果”は,母親の養育態度の誤りなどの特定の“原因”から生じていると認識する立場に立つことになりやすい.いわゆる“母原病論”に特徴的な発想である.このような認識論的な態度を持つセラピストは,当然,母親の養育態度を改善させるべく働きかけることになるだろう.しかし,現在ではこのような単純な因果論では,不登校の問題を理解できないことは,周知の事実となりつつある.このような限界のある直線的認識論に対比して,円環的認識論では,原因(母親の養育態度)と結果(子どもの不登校)とは相互に影響を与え合っていることを強調する.つまり,母子のいずれか一方の個体要因のみに力点を置く観点から,母子間の相互作用やコミュニケーション過程を重視する見方への転換である.これは,母子間相互作用を重視する現代の発達心理学の基本的な認識論とも一致している(久保、1995).
システム臨床心理学では,これを一歩進めて,両親間の相互作用や父子間相互作用といった他の2者間相互作用はもちろん,家族療法を用いる場合のように全家族成員間の相互作用までを視野に入れた接近法を模索している.これは,ある意味では“複雑系”としての家族システムを研究対象とする心理学が誕生しつつあるのといえるだろう(亀口、2000)。
21世紀の心理療法
ベイトソンの主張する円環的認識論に深い影響を受け、システム心理学を建設しようとしている臨床心理士は、以下のような理論的立場を取っている。
① 直線的思考よりは円環的思考を重視する.心理的問題や現象の因果関係は,一方向的・直線的ではなく,双方向的・円環的に捉えるべきだと考える。
② 因果律よりも“適合性(fit)”という概念に基づく思考法を採用する。
③ 問題(症状)行動の否定的解釈に対し,積極的に肯定的側面を加える。
④ “時間”の要因を重視する.なぜなら、生命系についての諸研究は,生命過程が常に不可逆的であることを強調しているからである。
⑤ “予測不能性”の概念を受容する.固定した目標に重点を置くよりは,偶然性に注目する。
⑥ セラピストを,クライエントに作用し,影響を与える“力”として見る立場を捨て、“中立性”を維持する努力を続ける。
⑦ “抵抗”についての伝統的な発想を捨てる.むしろ,“抵抗”をセラピストとクライエント(家族)の交流の一形態として理解する。
⑧ 均衡状態よりも不安定さを好むように,自己変革しようと努める。
⑨ 平衡維持(ホメオスタシス)の代わりに,“一貫性(coherence)”という新たな 概念を持ち込む。これは,システム内部および外部環境の両方向でのバランスが取れるように,システムの要素を一つにまとめあげることを意味している。
このような観点に立つ臨床心理士が提起しようとしているのは,進化的パラダイムであり,彼らの未来への強い志向性を示している。
サイバネティック認識論
キーニー(B・Keeney)は,生態システムを重視する立場を取り,“サイバネティック認識論”と呼ばれる認識論を提唱した。サイバネティック認識論ではクライエントや家族、あるいは所与の組織やシステムが問題をかかえていることに,責めを追わせようとはしない。“症状”を,生態系の比喩とみなし,ベイトソンが“謙遜と孤独”と呼んだ気づきの段階へと導く立場を取る。サイバネティック認識論における最も重要な概念の一つが相補性であるが,キーニ―はこれを“サイバネティック相補性”と呼んでいる。相補性や全体性を強調する点は,ユング心理学と共通している。しかし、ユング心理学が探求の出発点を“個人の精神内界”に置くのに対して,サイバネティック認識論では,“サイバネティック・システム”を対象とする。後者の立場では,人間に関わる事象は,無数の回帰的なフィードバック過程によって自己組織化されているとみなしている。サイバネティック認識論では,自己と他者(環境)との間に明確な境界は設定できないと考えている。したがって,親子間の相互作用のパターンを重視すると同様に,クライエント・システムとそれを支援しようとするセラピストあるいはコンサルタントとの相互作用パターンそのものに着目する。
認識論的立場の明確化
心理学研究を推進するうえで,研究者がいかなる理論を選択するかは決定的な重要性を持つ。システム心理学の分野でも同様であるが,心理臨床の実践場面においては,むしろ特定の理論へのこだわりが,クライエント・システムを共感的に理解し,有効に援助することを阻害する側面もあることが指摘されている。氏原(1992)は,臨床実践における知る働きと感じる働きの微妙な関係について的確な説明を与えている。氏原によれば,この知る働きを支えるのが理論であり,実践のプロセスそのものは主として感じる働きに左右される,と考えてよい。両者が,本来的には相補的でありながら,時に相反的に働き合うこともある。このように,二律背反の側面を臨床心理学は有しているが,これは対象とする心理現象(こころ)が,まさに“複雑系”であることに起因している。
システム心理学の実践においても,氏原の言う知る働きと感じる働きのバランスをどのように取っていくかが決め手になる。単に,誰それの理論に依拠するかいなかではなく,セラピストやコンサルタントとしての自分が,いかなる世界観や人間観を持って心理臨床の実践に携わるかを自らに問うことが求められる。リドゥル(Liddle,H.)は,そのような自己点検作業を“認識論的宣言(epistemological declaration)”と呼び,援助専門家にその実行を勧めている。システム心理学を実践する場合にも、われわれが,何をどのように知り,何をどのように考え,何をどのようにして臨床的決断を下すかについて,今後われわれ自身の特異性を明らかにする必要がある。