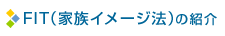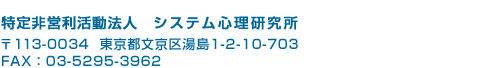システム実践学における逆説的アプローチ
システム心理学が対象とする人間のこころを,なぜ「複雑系」とみなすかと言えば、現実の心理的な問題解決において“逆説(パラドックス)”を無視できないことがあげられる.つまり,通常の科学研究が依拠する論理型では極力排除される“パラドックス”を,臨床心理の分野,とりわけ家族療法では重要視せざるをえないからである.家族臨床心理学の中核をなす家族療法の理論と技法は,このパラドックスという認識論上のてごわい相手とともに発展してきたと言っても過言ではない.ここでは,まず心理療法においてパラドックスがどのように利用されてきたかについて展望する.
実は、家族療法が一般化する以前から欧米の心理臨床家は治療技法としてパラドックスを使ってきたのである(亀口;1987,金沢;1985).たとえば、ダンラップ(Dunlap)は,“負の練習法”という逆説的技法を考案した.これは爪かみ,吃音あるいは夜尿といった症状のあるクライエントに,それを面接場面で実際に再現するように指示する方法である.
実存分析のフランクル(Frankl)は,”逆説的意図”という技法を提唱し,患者が恐れているまさにそのことを行うように,あるいはそのことが起こることを期待するように患者を激励した.彼は,神経症的な悪循環に陥っている患者が,逆説的意図を自覚することで,
その悪循環を断ち切れると考えた.
論理療法のローゼン(Rosen)は,患者が異常な行動を始めると,その症状を最も派手な形で表し続けるように患者に指示した.この技法は,患者が自分の症状を受け入れられるように援助するのに加えて,症状の再発を防止することを目的としていた.ローゼン(Rosen)は,この技法を“精神症状の再現法”と呼んだ.
ゲシュタルト療法でもパラドックスが使われている.ゲシュタルト療法では,人が真に自分自身になる時こそ,内的変化が生じると考えている.そこで,セラピストが変化の担い手になることを避け,逆にクライエントに対して今の自分になりきるように要求することによって,変化がもたらされる.
ファラリー(Farrelly)は,逆説的な方法を用いた独特な心理療法を発展させている.このアプローチは,クライエントに強い感情を引き起こすために“挑発療法”と呼ばれている.このアプローチは,症状を誇張する点に特徴があるが,治療要因の鍵になるのは,ユーモアである.この療法の作用機制を説明する仮説には,クライエントの拒否的態度には使い道があるとの前提がおかれている.
パラドックスを用いる心理療法の先駆のなかでも,ミルトン・エリクソン(Milton Erickson)とパロアルト・グループの貢献は,特筆すべきである.彼らは,二重拘束理論を構築し,精神障害におけるパラドックスの病理的側面に焦点を当てたが,同時にその治療的応用の可能性についても力説している.ヘイリー(Haley)を通じてパロアルト・グループに大きな影響を与えたエリクソンは,催眠と心理療法においてパラドックスを巧みに利用したことで知られている.基本的に,人々の行動を肯定的に表現し直すことで,治療的変化を生みだそうとした.彼は,直接的方法ではなく,遠回し,あるいは間接的な影響を与えることで変化を引き起こした.
家族療法におけるパラドックスの利用
パラドックスを積極的に用いる家族療法は,セルヴィニ-パラツォーリらのミラノ学派によって推進された.彼らは,家族療法の学派のなかでもベイトソンのシステム論的認識論の影響を最も強く受けており,統合失調症や他の重い精神病患者の家族に対してもパラドックスを実に巧みに使った治療的介入を行い,劇的な効果をあげている(Selvini-Palazzoli,et.al, 1978). 先駆的なものを除けば,パラドックスを用いた接近法が,治療技法としての形態を取るようになって,まだ20余年ほどの歴史しかない.しかし,家族療法のみならず,他の心理臨床の学派でも,この接近法に対する関心は急速に高まっている(Seltzer,1986).二重拘束理論に見られるように,時には精神病の発生要因にもなりうるパラドックスが,使い方によっては困難な心理的な問題を解決する有力な手段になると期待されている.まさに,これはパラドックスそのものであり,心という“複雑系”を扱う心理臨床にこそふさわしいものかもしれない.
パラドックスを用いる技法は,一般にはセラピストがその権威を背景にして,クライエントに尋常でない課題の遂行を強いる一種のショック療法のようなものだと誤解されている面がある.しかし,実際には,むしろセラピストは控えめな態度を取る.とりわけクライエントの抵抗を前提とするパラドックス技法では,セラピストはクライエントに容易に押し返されてしまう.ところが,結果は症状の改善へとつながる変化が生じる.まさに“負けるが勝ち”であり,“柔よく剛を制す”,あるいは相手の気力を逆に利用することで,非力な者が強者を倒す合気道の世界の論理に通じるものがあるとされている.
パップ(Papp)は,家族療法で有効に用いられるパラドックス技法として“逆転法”を提案している.この方法は,家族成員の一人に,ある重要な問題に関連した行動を,それまでとは逆にするように指示し,それによって他の家族成員の逆説的な行動変化を引き起こすことをねらったものである.そこでは,セラピストから指示を受ける家族成員の同意と,指示の結果を受け取る他の家族成員の反抗が共に前提になっている.逆転法は,反抗的な子どもをかかえて苦悩する両親を援助する際に,とりわけ有効性を発揮する.両親がセラピストの指示に積極的に従うことによって,短期間で顕著な変化が生じ,子どもが反抗的態度を止め,家族関係を改善できた事例が報告されている(Papp,1980).亀口(1985)も,登校拒否の家族療法事例でパラドックスを用いて問題解決を図った治療機制について詳しく検討している.
パラドックスを用いる技法の場合,セラピストが権威的に問題行動を処方するのではなく,問題行動それ自体が家族システムの平衡維持にとっては,肯定的な役割を果たしている側面を評価したことに意味がある.つまり,一種の二重メッセージとして与えている.したがって,家族全員が同時にセラピストの発言を聞いていても,各人の受け取りかたは,微妙に違ってくる.ちょうどロールシャッハ反応のように,セラピストのメッセージに対する各人の認知的差異が浮き彫りとなり,相互の関係認知が明確化する.ここから,家族が陥っていた悪循環を断ち切る潜在的可能性が生まれてくる(Keeney &Ross,1985).
家族システムへの臨床的接近法
円環性
心理療法の他の接近法と同様に,家族療法においても面接過程の詳細な分析・検討がなされている.とくに,ベイトソンの主張する円環的認識論に基づくミラノ学派の開発した“円環的質問法”は,国際的に大きな影響を与えてきた.この質問法の特性は,“円環性”にあるとされている.ミラノ学派によれば,円環性とは,面接実施中の活動過程であり,セラピストと家族が構成する拡大システムの中で発生する特性である。キーニ―は,円環性についての説明の中で,パターン化された回路で作られ,情報を生み出す“差異”が詰め込まれたシステムの円環性について言及している.たとえば,ある一つの回路を取り上げても,多くの方向へ円環を描くことができる.それは,単純なレベルの場合もあれば,非常に複雑なレベルの場合もある.治療面接では,セラピストとクライエントとの間で発生してくる社会的フィードバックについても同様の理解が可能である.したがって,この回路は“心の単位”であり,情報が引き金となって起こす差異によって作られている.このサイバネティックな観点では,システムのいかなる部分も他に対して一方的な支配力を持つとは考えられていない.各部分の行動は,それ自身の過去の行動と同じく,他の部分の行動によっても決定されるからである.
ある症状をサイバネティック回路の部分として見ることは,“症状”と呼ばれている事象を内に含むフィードバック構造を有する出来事の円環的(循環的でもある)連鎖を認めることを意味している.同様に,“介入”をシステミックに見ることは,介入をそのループ内に含む,サイバネティック回路を構成することを前提としている.また,ミラノ学派が常に強調するようにこの回路の中には,セラピストが必ず含まれている.治療的変化は,クライエントの側にもセラピストの側にも生じることを前提としている.
円環的質問法の展開
円環的質問法は,円環的認識論に基礎を置く家族療法の実践を通して創案された独創的な面接技法であり,ペン(Penn)らによって定式化された.その後も,世界各国の家族療法家によって改良や理論的発展が継続的に行われている.ここでは,ペンの円環的質問に関するパターン分析について紹介する.
一般的に言って、円環的質問法はさまざまな順序で実施される.たとえば,過去についての質問から始めて,現在に来たり,現在の話題から始めて過去に戻ったりする.これは,円環的質問によって引き出される家族からのフィードバックや反応によって変わる.円環的質問を通して浮かび上がってくる家族関係のパターンは,家族の中で問題が発生してくる経過と構造的に等価であり,同形的なものだと考えられている.円環的質問法の目的の一つは,システムの歴史の中で重要な同盟関係が変化しはじめた時点と,その変化に伴って家族に問題が生じてきた時点とを同定することだとされている.円環的質問法によって探し出された情報は,その問題が始まった時点の前後で,その家族が体験した関係の“差異”である.ペンは,過去と現在をつなぐ“弧”を行き来するために使う円環的質問の類型を,以下のように列挙している.
(1)言語的および類比的情報
言語情報に関しては家族が使う“キーワード”に注目することが有益とされる.とくに,問題を説明するせりふの中に埋め込まれた“キーワード”を発見し,家族内の関係とその“差異”に置き換えていく.“母親が自分を責めているときに,誰が一番そのことを心配しますか”,あるいは“家族の中で一番話をしないのは誰ですか”などが,その実例である.面接の進行とともにセラピストと家族の間で副次的主題が進行していく.それは,互いの目つき,姿勢変化,口調あるいは介入のタイミングなどの行動上の指標に現れてくる.この副題のやり取りと言語情報の集積によって,セラピストと家族の間に共進化のループが形成される.
(2)問題の定義
“今のあなたがたの問題は何ですか”というセラピストの最初の質問は,一つの弧の端を決める作業であり,面接の後半部で,問題が発生した過去のある時点と連結される.
(3)現在の同盟関係
問題を定義した後の課題は,現在の問題をめぐる同盟関係を識別することである.
(4)異なる連鎖
問題が起こった時に,家族がどのように行動するかについて尋ねる.この情報によって家族の同盟関係や関係のパターンを明らかにすることができる.
(5)分類と比較の質問
現状と過去の比較をさせたり,親密さの違いを尋ねたりすること.この質問は,家族の間で同盟関係がどのように変化してきたのかを確認するために組み立てられる.
(6)同意の質問
セラピストは,この質問によって同盟の強度や優先順位を判定できる.
(7)面前でのうわさ
家族内の三角関係についての情報がさらに必要な場合には,この質問を使う.これは,家族の一人に他の二人の関係についての意見を求めることである.これを順次繰り返すことで,全体の関係認知の構造が浮かび上がる.
(8)サブシステムの比較
サブシステムの比較は,多様な目的を持っている.サブシステム比較の特殊分類は,“もし”で始まる質問である.これは治療的介入の準備としても使われる.これは,家族内での変化の結果を予測するものであり,それ自体が強力な介入の力を秘めている.
(9)説明的質問
セラピストは,家族からのフィードバックを参考にしながら説明的質問のパターンを取り始め,現在に向かって作業を進め,あるいは,逆に現在についての質問から始めたのであれば,過去に向かって作業を進める.説明的質問は,“~をどう説明しますか”と聞くだけのものであるが,家族の反応を手がかりにして作業仮説を立て,治療的介入を考案する合図にもなる.
このような下位分類を持つ円環的質問法の利点としては,適切な仮説を設定したり,適切な介入を行うために必要な情報を集めるために有効な技法であること,また同席している他の家族成員の考え方や感じ方を相互に知ることによって,家族自身が自分たちのことをシステミックに見る機会を与えること,などの諸点が指摘されている.さらに,家族が相互に関連している行動への気づきを深めることは,貴重な自発的変化(自己組織化)を引き起こすきっかけにもなる.
トム(Tomm)は,円環的質問の類型をさらに綿密に分類している。さらに,トムは円環的質問を適切に用いることによって,それ自体が治療的な効果を発揮し,特別な儀式を処方したり,介入を意図した課題を与えなくとも,家族システムに自発的な変化を促すことが可能だと主張している.また,ミラノ学派は次々に質問法の改良案を発表し,他のシステミック・アプローチを取る家族療法家もそれぞれに独自の面接技法を開発している.亀口・萩原(1987)も,“日本語”による円環的質問法の確立を目指して臨床事例を蓄積している.また,十島(1997)は,第3世代のシステム論とされるオートポイエーシスの観点から,面接場面のコミュニケーション過程を分析している.とりわけ,家族コミュニケーションの“生死”と,家族の機能水準の良否とを直結させて論じようとする試みは注目される.
学校システムへの臨床的接近法
学校システムの危機
現代日本の学校が抱える問題として,80年代前半の校内暴力を経て,90年代後半になるといじめや登校拒否(不登校)が急増し,社会的にも注目を浴びるようになった.文部省の学校基本調査によれば,1999年度に30日以上の登校拒否(不登校)が確認された小・中学生は,13万人と過去最高を記録したとのことである.児童・生徒数が過去最低となっている一方で,登校拒否が急増する現状は,学校システムが危機に陥っていることを如実に示していると理解してよいだろう.心理学の研究課題としてもきわめて重要性の高いものであり,とりわけ臨床的接近法が有効な領域である(亀口、1991a).
弘中(1990)は,“今日の登校拒否の問題は,狭い意味での<心の治療>,伝統的な心理療法の治療構造の枠には収まりきらない諸構造を抱えていることは確かといえよう.では,今日の登校拒否をどうとらえるべきなのか,どのような対処が望ましいのか,前述の様々の論点を十分に検討した上で,有効性のあるマクロ的,ミクロ的なモデルが提出されるのが望ましいのであるが,それがまだまだ不足しているのが現状である”と述べている.
心理学関連の学会での,登校拒否に関わる研究発表の件数は増加傾向にあるものの,複数の査読者の査読を経て学会機関誌に掲載された登校拒否関連の学術論文の数はきわめて少ない.問題の社会的重要性から見ると,この状況が好ましいものとは思われない.
平岡(1989)は,中学生の登校拒否児に対する環境療法を行った事例を詳細に検討している.この論文では,個人,家族,治療環境,地域といった登校拒否問題を取り巻く多層的なシステムのレベルに配慮した考察がなされており,平板な事例研究の枠を超えた説得力を備えたものと評価できる.今後,この種の論文が数多く公刊されることが期待される.
室田(1997)は,登校拒否(不登校)の長期にわたる追跡研究を行っている.その結果によれば,学校復帰できた子どもでも,その後の適応状態が良好であったものは全体で60%にすぎなかった.この結果についてはさまざまな解釈が可能であるが,すくなくとも学校復帰した児童・生徒に対する学校側の対応が万全のものであるとは言い難い.現在の学校システムが,登校拒否の問題解決に有効な手段を見出しえていない現状が明確になったといえるだろう.
個々の事例について詳しく見ていくと,同じ登校拒否児であっても性格や行動特性,能力はさまざまであり,家庭的背景についても一様ではない.また,従来の学校問題と異なり,教師が積極的に問題解決に乗り出すことで,かえって不登校状態を長期化させてしまう事例も少なくない.むろん,放置してしまって良いわけでもない.登校拒否の問題については,ベテランの教師でさえも対応に苦慮しがちである.
このような登校拒否問題の複雑さを考えると,児童・生徒が長時間生活する環境としての学校に内在する問題性を無視することはできない.そこで,システムとしての学校の病理性もしくは,問題性に目を向けることになる.最近では,登校拒否児を一部の例外的な子どもと見て対症療法的に対応するだけでなく,もっと積極的に潜在的な“学校嫌い”の子どもをも視野に入れた対応策を研究する必要性が指摘されるようになってきた.
その際には,学級,学年,管理職,事務職などの学校システムを構成するサブシステムの個別の人間関係に目を向ける必要がある.“全体としての学校システム”の問題を,制度の問題としてよりも児童・生徒と教職員のメンタルヘルスの問題として取り組む必要性も指摘されている(飯長、1989).
学校システムへの臨床的接近
さまざまな心理的問題をかかえた現代の学校システムの再生を図るためには,実践的研究とともに基礎研究の充実も急務である.この役割をになう心理学の領域は“学校心理学”である.石隈(1994)は,学校心理学の専門家としてのスクール・サイコロジストと学校心理学に関する心理学的研究の展望を行っている.その中で,スクール・サイコロジストの行う援助的介入として,従来のカウンセリングだけでなく,コンサルテーションが重要視されつつあることを紹介している.スクール・サイコロジストの行うコンサルテーションには,問題解決型,研修型,システム介入型などがあるとされている.
とりわけ,システム介入型のコンサルテーションは,学校システムを再生するための有力な社会的資源として期待されている.スクール・サイコロジストは,学校教育システム全体の心理教育的コンサルタントとして,学校が児童・生徒の学習と発達の場所として最高に機能するように働きかける.教育目標の設定,プログラムの開発と評価,生徒の学習面での問題に対する予防的対応などで,学校経営者(校区の教育長や校長など)に協力する.
学校コンサルテーションで使われるモデルとしては,生態学的コンサルテーションと精神保健コンサルテーションがあるとされている.いずれのモデルを使うにしても,コンサルテーションにおける人間関係では,専門家としての信頼性と人間としての魅力の両面が要求される.しかし,この分野の研究は,先進国のアメリカでもあまり進んではいないと言われている.文化社会的な差異を考慮すれば,教師とスクール・サイコロジストの分業や協同のあり方も,わが国独自の方式を工夫しなければならない.このような実践的側面でも,やはり判断の基礎となる実証的な心理学的研究の発展が期待されている.いずれにしても,臨床的接近法と基礎研究の相補的発展が課題である.
学校と家庭の連携
校内暴力,いじめ,登校拒否といった子どもをめぐる問題のいずれの対応策についても,学校と家庭の連携の必要性が指摘されないことはなかった.にもかかわらず,多くの場合はそれが掛け声だけに終わっていた.相互に,異なる組織や制度の枠組みを破ってまで,問題解決のために協調・連携することは,それだけ困難な課題なのである.
近年,ネットワーキングという新たな組織論が登場してきた(金子,1986).これは,民間ボランティアによる草の根運動に見られるような,従来の硬直したタテ割りの組織や制度にしばられない,人々の自発的で柔軟な連携や協同作業の進めかたを指している.このネットワーキングの発想によって,共に感情を持った生身の人間が構成している学校システムと家族システムの連携,すなわちシステム・ネットワーキングが可能になる.事実,アメリカでは,Steele(1991)らが,さまざまな心理的問題をかかえた児童・生徒のいる家族を援助するために,学校の教職員を主体にした積極的な介入プログラムを構築して成果をあげている.
わが国でも,数年前から各地の教育委員会に登校拒否対策を目的とした協議会が設置され,各関係機関の連携が図られるようになってきた.たとえば,北九州市では教育委員会の呼びかけによって,“学校嫌い等不適応対策協議会”が設置されている.この協議会は,市内全域の学校と家庭及び児童相談所や福祉事務所などの福祉・医療の専門機関をネットワークすることによって,学校嫌い等の不適応問題の解決を図り,これらの問題についての正確な認識を広めようとしている.この協議会には臨床心理学者がコンサルタントとして加わり,学校システム内部のみならず家族システム内部のネットワーキングの確立をはじめとして,各関係機関相互のネットワーキングに積極的な提言と心理教育的援助を行っている.
さらに,いじめや不登校の問題の急増に対応するために,文部省が1995年以降,スクールカウンセラー事業を開始したことによって,学校臨床心理士の活動が全国の学校に広がり,次第に社会的認知を得つつある(村山、1997).
予防研究における臨床的接近法
予防科学の時代
わが国とは比較にならないほど多様な臨床的接近法が発展しているアメリカにおいても,精神保健の促進や精神疾患の予防については,心理学研究者はあまり積極的な関心を向けていなかった(Heller,1996).しかし,急増する社会的ならびに心理的問題に対するアメリカ国民の苛立ちが強まるにつれ,ごく最近では効果的な予防プログラムを切望する気運が心理学界にも高まってきた.
この社会的状況の中で,次第に“予防科学”と称される科学の新分野が登場しはじめている.この用語は,1991年に開催されたアメリカ精神保健研究所(NIMH)主催の全国予防会議で提案され,“危険要因や保護要因と呼ばれる障害や健康の前兆について組織的に研究することに主眼を置く研究領域”と定義された.基礎的な危険要因研究と統制された介入試験との間で相補的な役割分担が必要だと指摘された.基礎研究は予防的な介入のデザインに有効な情報を提供し,片や介入を意図した臨床実践の成果は,危険性や抵抗に関わる要因についての何らかの洞察を与えるだろうと期待された.
障害の前兆としての危険および保護要因に研究の焦点を当てることについては,異論がないわけではない.ランズマン(Landsman)は,個人の危険要因に方向づけられた障害予防のモデルは,行動に埋め込まれた生態学的要因を無視していると指摘した.ペリーら(Perry &Albee)は,予防モデルが社会的な不正義や貧困や社会階層と精神障害の発生率とを関連づける疫学的な証拠を無視していると批判した.しかし,ヘラ―(Heller)は,予防科学が政治的な論争に巻き込まれてしまわないためにも,実証的な研究が不可欠だと主張している.
予防研究における心理学の役割
レイスら(Reiss & Price)は,心理学の各分野が,来るべき予防科学の時代に大いに活躍するだろうと予言している.それらの分野は,臨床,コミュニティ,発達,社会,組織,そして健康心理学だと指摘した.同様に,他の広範な心理学の専門領域がそれぞれに独自の見通しや科学的な技能を予防科学の企てにもたらすことができる.さらに,1994年に新設されたAPA附属の学校・教育心理学センター(CPSE)は,学校問題の改善にも心理学が大きな貢献を果たしうると主張している(Talley &Short,1995).
予防の分野は,心理学の科学者側にもまた実践家側にも,豊富な機会を提供できるだろうと期待されている.実践家にとっては,有効な予防プログラムの開発によって新たな予防的サービスをコミュニティに提示できる.研究を主とする心理学者にとっては,試験的な介入の効果を測定することが,発達過程や因果メカニズム,そして人生設計や幸福の形成において社会的文脈が果たす役割についての新たな洞察を得ることができる.NIMH報告(1995)は,予防科学が将来的には極めて広範な目標に向かって発展するだろうと予測している,人間発達についての最良の科学的研究,介入の科学における最も効果的なアプローチ,そして人間社会の望ましい機能に必要な条件に関する啓発的研究の3領域を連結させることが,その目標になるだろうとみている.
以上のように,予防研究を始めとする今後の心理学研究の方向性を考えた場合に,臨床的接近法の果たすべき役割はさらに重要性を増すと予想される.しかし,それが基礎研究から遊離したものであってはならないことは,明白である.両者の相補的な発展が何よりも望まれる.
産業システムにおける臨床的接近法
産業カウンセリングの現状と課題
前述した家族および学校システムにおける種々の病理現象の増加に、巨大化した産業システムに内在する病弊が無関係であるはずはない。とりわけ、バブル経済の崩壊や、その後の産業構造の転換に伴なう、リストラの増大や終身雇用制度の揺らぎは、われわれ日本人の心の有り様や人間関係の根底を脅かすほどの影響を与えつつある。従来から,各産業システム内部でもカウンセリング・サービスが提供されてきた。しかし、それはあくまでも、周辺的あるいは副次的なものであり、産業システムそのものがかかえる病理構造を視野に入れた取り組みではなかった。 これまでの産業カウンセリングが前提としてきた基本的態度は、あくまでも各産業システム内部の構成員の個々人がかかえる悩みや心理的障害に対して援助の手を差し伸べようとする趣旨のものであった。したがって、産業システムそのものに内在する、いわば、「システムの心理的問題」あるいは「システムの病理」をカウンセリングの対象とするような要請や発想は、どこからも出てくる余地はなかったといえるだろう。しかし、バブル経済崩壊以降の日本経済の停滞につづき、社会システムのほぼ全域にわたるほどの「制度疲労」を一般大衆にも印象付けるような事件・事故の多発によって、「戦後システムの病弊」が次第に指弾されるようになってきた。産業カウンセリングも、個人の悩みに対応するだけではなく、産業システムそのものが直面しつつある構造変革の危機にも目を向け、臨床的に接近するための理論と技法を生み出す必要性に迫られている。
これからの産業カウンセリング
21世紀は「こころの時代」ともいわれている。これからの産業システムにとって、カウンセリングは欠くことができない要素となりつつある。その実務に当たる産業カウンセラーや臨床心理士の志望者は急増している。いまでは、多くの高校生が希望する職種の上位にランキングされるほどの人気を集めつつあるようだ。
産業カウンセリングに対する一般のイメージを要約すれば、企業に働く従業員を対象にした相談活動で、個人の不平不満や悩みを聞き、問題可決を援助するといったことであろう。しかし、日本産業カウンセリング学会の杉渓一言会長も指摘しているように、これは人間関係管理の方策として企業に導入された従来型の産業カウンセリングである。生産性向上を第一に考えていた高度成長時代の企業は、産業カウンセリングをあくまでもその枠組みのなかでとらえ、位置づけていたのである。
当時は、労使間の葛藤や対立はあったものの、従業員の精神的健康にかかわるような問題は企業一家の繁栄のなかに包み込まれ、多くの産業カウンセラーは相談室のなかでもっぱら「聞き役」を演じていた。しかし、時代の急速な変化が日本の産業組織の構造変革を促がし、産業カウンセリングの環境も大きく変わってきた。
今までの産業カウンセリングは相談室という、いわば密室で行われてきたが、これからは組織、社会に向けて開かれた活動が求められるようになるだろう。カウンセリングの対象も、経営者から新入社員まで、組織に働く勤労者のすべてを含み、さらにはその家族も視野に入れることも必要になる。
産業カウンセリングにおける「産業」の概念についても、再考が迫られている。一般的には、産業イコール企業と見られている。事実、日本産業カウンセリング学会所属のカウンセラーの多くは、企業カウンセラーである。しかし、学校、病院,各種団体、公共体、施設などのカウンセラーも含まれている。そこで、産業の概念を拡大し、勤労者を対象にしたすべての「組織体」あるいは「産業システム」として捉えるほうが、より適切ではないだろうか。産業システムを、社会システムを構成するサブシステムとして位置づけることによって、前述した家族システムや学校システムなどの生身の人間が構成する「生きたシステム」の文脈に組み込むことも可能になる。
システム論的カウンセリング技法の導入
いうまでもないことであるが、各種の産業システムで働く勤労者の活動の源泉はまず家庭生活の充実であり、その基盤が確立していなければ、豊かな創造力も仕事に対する意欲も出てこない。ある従業員が遅刻や早退が多く、関係部局の士気に大きな影響を与えているとき、家族療法を学んだカウンセラーならば、まずその従業員とその家族の面接を通して家族内の力動的な関係や葛藤についての理解が得られ、有効な対応策を見出し、無用な混乱を未然に回避することもできるだろう(楡木、2000)。
しかし、楡木も指摘しているように、産業カウンセラーが家族療法を学んで得られることは、このような直接的効果だけではなく、むしろシステム論の本質的理解からもたらされるシステム思考やシステム的認識法の習得にある。20世紀後半に、システム理論はまず家族問題に取り組んで発展し、そこからさまざまな理論や原理が生み出された。これは、家族内での葛藤がわれわれの身近にあり、解決すべき問題としてとりあげられやすかったからにほかならない。もし産業カウンセラーがシステム論を本格的に学ぶならば、企業もシステムとして機能していることを実感的に理解するだけでなく、企業内で生じているもろもろの現象をシステム論の立場から再考することもできるようになるだろう。
今後、家族システム論を学んだカウンセラーが、職場の小集団についての諸問題をはじめとして企業組織体の構造や機能などさまざまな方面で、先導的な役割を果たすことが期待される。